9月5日(金)は、いわき市役所の創生推進課から外部講師3名をお招きし、「考えよう、いわきの将来を 地方創生に向けて」をテーマとして講話をいただきました。


全国的にも問題となっている人口減少に関して、なぜ人口が減るのかという構造的な問題点とそこから生じる課題と対策について詳しく伺いました。


いわき市の人口は現在、約31万人まで減少しており、2050年にはさらに19万人台になると推計されています。そこで、現在いわき市ではいわき創生総合戦略を立て、まちの活力維持を目指して行政・民間・市民が連携することを目指しています。持続的な魅力で人を呼び込むために必要な視点として、「他にはない、いわき市独自の魅力とは何か?」を持つ必要があることを強調されていました。


いわき市の独自の魅力として講師の方が挙げたのが「フラ文化」と「自然の豊かさ」です。スパリゾートハワイアンズの開業以来、フラダンスが根付き、高校生の全国大会「フラガールズ甲子園」も開催され、いわき市は「フラガールが生まれたまち」として全国的に知られています。 また、いわき七浜と呼ばれる海岸線、阿武隈山系の渓谷、温泉など、海・山・川の恵みも豊かで、四季折々のアクティビティが楽しめるなど多様な魅力がいわき市の強みでもあり、こうした魅力を発信していく必要性を生徒たちも理解しました。
9月12日(金)は、いわき市役所の政策企画課から外部講師2名をお招きし、「いわきのいま・むかし・これから」をテーマとして講話をいただきました。

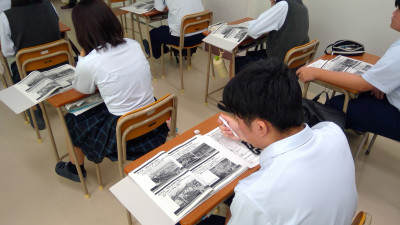

いわき市のルーツとして、常磐炭鉱の歴史を詳しく解説いただきました。石炭は「黒いダイヤ」と呼ばれ、地域の経済を支え、人口増加やインフラ整備を促進させましたが、戦後、エネルギー革命により炭鉱は衰退。昭和40年代の閉山ラッシュで多くの坑口が姿を消しました。これからのいわきは人口減少・少子高齢化が進み、公共施設の維持が難しくなる課題が指摘されています。



いわき市は「well-beingなまちづくり」を目指す政策を推進中とのことで、今後5年間での政策の指針についてご説明をいただきました。
ヒトづくりをベースにコンパクトでも幸福度の高いまちを目指す必要性を生徒たちもデータから考えることができました。
9月19日(金)は、いわき市役所の産業みらい課から外部講師1名をお招きし、「いわき市を支えるものづくり産業」をテーマとして講話をいただきました。


いわき市の工業史では石炭鉱業の隆盛と斜陽化、重化学工業への転換に伴う工業都市への変貌についてお話を伺い、いわき市各地に点在する工業団地と製造業の特色、地元企業についてご説明をいただきました。また、これからのいわき市を支える産業として、ロボット、ドローン、エネルギー・環境分野の次世代産業の活性化を目指し、福島イノベーション・コースト構想を推進しているという話を伺いました。


実業系の学科である水産科や商業科ではなじみのあるイノベーション・コースト構想ですが、普通科はなかなか触れる機会がないため、生徒たちにとっては県が推進する事業の理解を深められたと思います。


それぞれの授業の締めくくりには、講師の方々から生徒たちへ探究課題(テーマ)をご提示いただきました。テーマを通して地元理解を深めつつ、将来のいわきについて、自分事として捉え、課題解決に向けた取り組みの在り方を考えていきたいと思います。
ご講話いただいた講師の皆様、ありがとうございました。